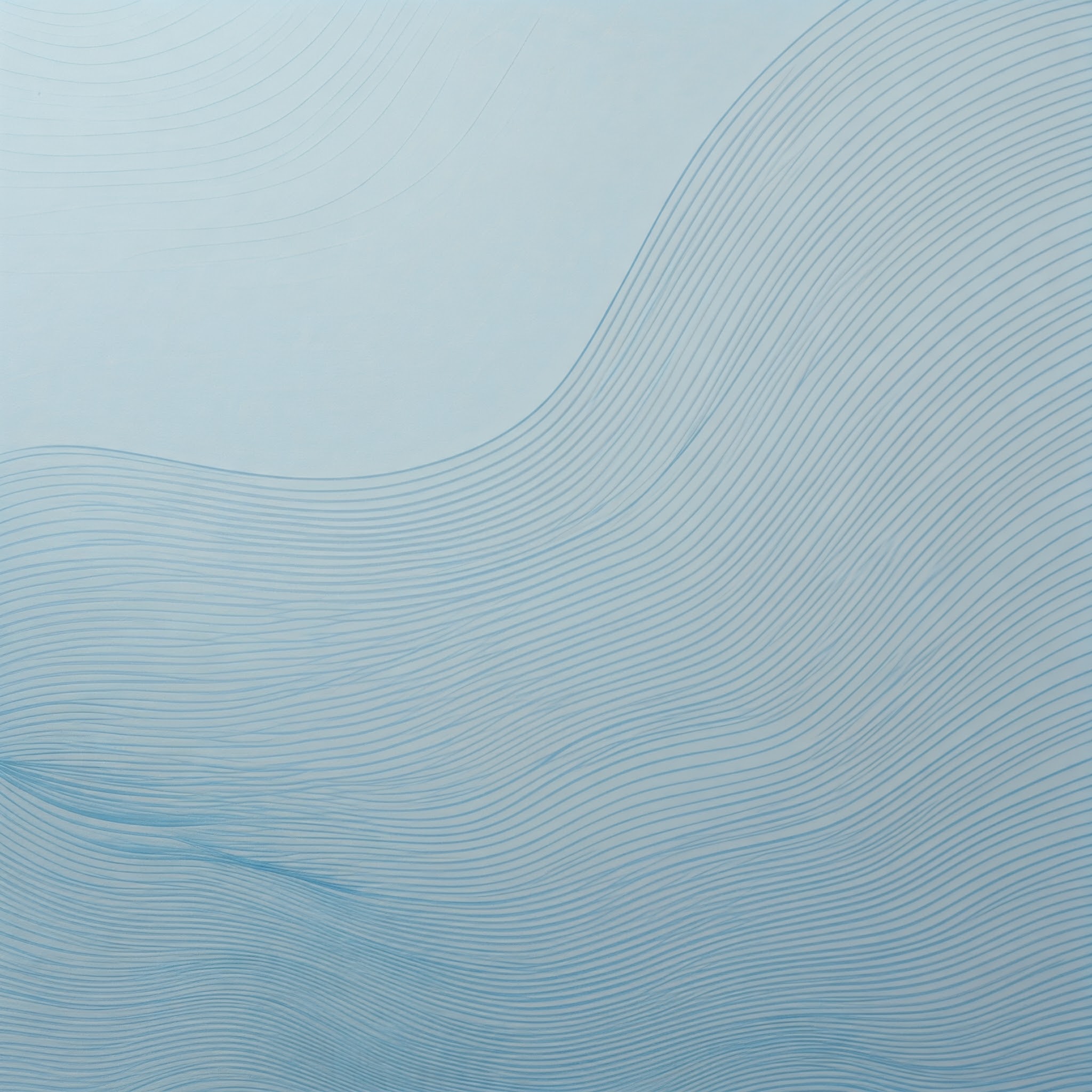こんにちは!皆さん、学校の「社会」の授業は好きですか?歴史や地理、公民など、私たちの社会について学ぶ大切な科目ですよね。
でも、おじいちゃんやおばあちゃんの時代には、今の「社会」とは違う授業があったって知っていましたか?今回は、そんな昔の授業について、先生と生徒の対話形式で探っていきましょう!
先生と生徒の対話
生徒: 先生、学校の「社会」って科目、戦前は「修身(しゅうしん)」っていう科目だったって本当ですか?
先生: うん、その通りだよ。戦前の日本では「修身」という科目が存在していて、今の「社会科」とは役割が違っていたんだ。
「修身」ってどんな科目?
先生: 修身は、明治時代から第二次世界大戦終戦まで、学校教育の中心的な科目だったんだ。目的は、主に「忠」(国や天皇への忠誠)、「孝」(親への孝行)、「礼儀」といった国民道徳を教え、品性や徳性を養うことだったんだよ。
生徒: へえ!じゃあ、今の「社会」の授業と全然違うんですね。今の社会科って、歴史や地理、公民を総合的に学ぶ科目ですよね。
先生: よく気づいたね。その通りだよ。第二次世界大戦後、修身は軍国主義教育の一環とみなされて廃止されたんだ。そして、民主主義社会に生きる市民を育てることを目的とした新しい科目として「社会科」が新設されたんだよ。社会科は、社会の仕組みや多様な価値観を理解して、主体的に社会に参加する能力を育むことを目指しているんだ。
「倫理」は「社会」の一部?
生徒: なるほど!そうすると、「倫理」って今の社会科の一部なんですか?なんだか難しそうだけど、修身とも関係があるのかな?
先生: いい質問だね。うん、現在の日本の高等学校教育では、倫理は公民科という社会科の一分野に含まれているんだ。公民科には「倫理」の他に「現代社会」や「政治・経済」といった科目があるね。
生徒: じゃあ、社会科に倫理があるのは、修身が前身だからってことですか?
先生: そこが少し違うんだ。修身は「国家の求める道徳」を教える性格が強かったけれど、今の社会科の「倫理」は、特定の価値観を押し付けるのではなく、多様な倫理観や思想に触れることで、生徒自身が自らの倫理観を構築していくことを促す役割を担っているんだ。
大学の哲学と教育勅語
生徒: ちなみに、大学だと哲学とか倫理って文学部にありますよね。それは戦前から変わらないって聞いたんですけど。
先生: うん、その理解で合ってるよ。大学の文学部で哲学(倫理)が扱われるのは、戦前から変わらない学問分野としての位置づけなんだ。大学は、初等・中等教育とは違って、特定の思想を教え込むことよりも、学術的な研究と真理の探究が主な目的だったからね。
生徒: じゃあ、戦前の大学の哲学科では、小学校で教えてた「教育勅語」なんて全然関係なかったんですか?
先生: まったく関係なかったと言っていいだろうね。教育勅語は1890年に発布されて、国民が守るべき道徳の規範を示したものだけど、これは主に初等・中等教育の「修身」を通じて、国民に徹底的に教え込まれたんだ。大学の哲学科は、より普遍的な人間の存在や社会、価値観について、批判的・多角的に考察する独立した学術機関としての性格が強かったんだよ。
初等教育と高等教育の違い
生徒: そう聞くと、戦前の小学校と大学の教育って、全然違う役割だったんだなっていうのがよくわかりますね。
先生: よく気づいたね。まさにその通りだよ!戦前の日本では、初等教育と高等教育の間には明確な目的と内容の差があったんだ。
先生: 初等教育は、国民としての基礎知識と、国家が求める道徳観を身につけさせることに重点が置かれていて、全ての国民が受けるべき義務教育だったんだ。一方、高等教育は、学術研究を深めたり、専門的な知識を持つ高度な人材を育成したりするのが主な目的で、一部のエリート層が対象だったんだよ。
先生: 同じ「倫理」というテーマでも、初等教育の「修身」が国家が定めた規範の実践を重んじたのに対し、大学の「哲学(倫理学)」は普遍的な人間のあり方を多角的に考察する学問として扱われたんだ。
まとめ
今回の対話で、戦前と戦後の教育、そして初等教育と高等教育の違いが見えてきたのではないでしょうか。
教育は時代とともに変化し、その目的や教える内容も変わってきました。昔の教育を知ることで、今の教育がどのような経緯で形成されてきたのか、より深く理解できるかもしれませんね。